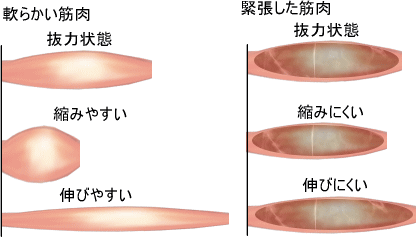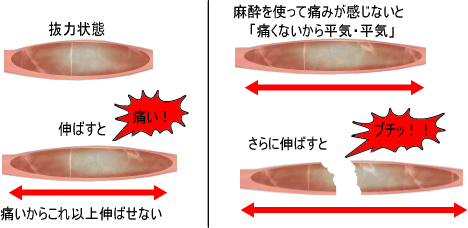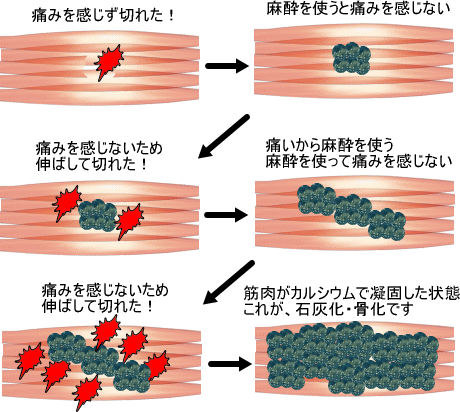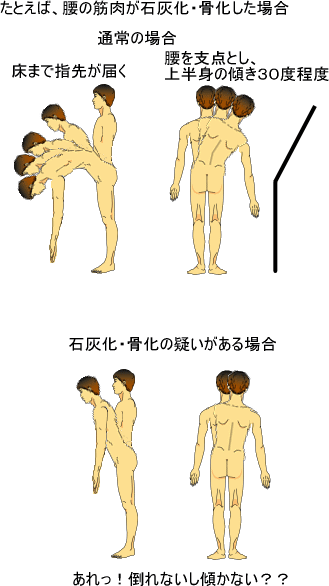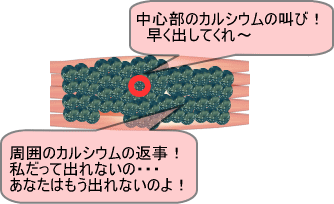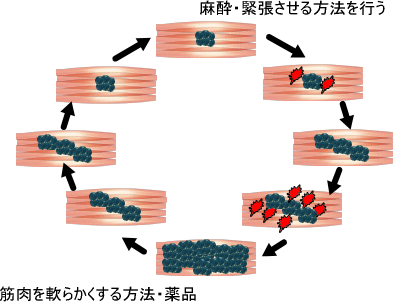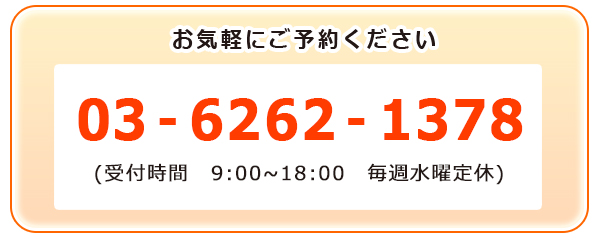病院・整骨院・整体・鍼灸などの治療・体操しても、腰痛・肩こり・関節痛が治らない場合、自分で簡単に出来る『らくらく改善法』の動画を用意しましたので、是非お試しください。
2、筋肉を動かさないために起こる緊張 ※血液検査で、炎症反応が起らない。
これが一般的に言われる慢性疼痛(慢性的に痛みが続く)の原因です。
筋肉を緊張させている緊張成分が、筋肉から排出されず滞るため、いつまでも筋肉は緊張し続けます。
そして、緊張した筋肉は伸縮しづらいため、その周辺の筋肉は今まで以上の運動を必要とし、さらに緊張し続けます。
緊張する筋肉の範囲(体積)は、どんどん大きくなります。まさに悪循環。
痛みは筋肉の緊張ですから、緊張した筋肉がさらに多くなれば痛みが増します。
【補足】わかりやすい説明として
筋肉を動かさないために起こる緊張とは、脳梗塞などにより寝たきり状態になっている患者は筋肉が緊張し、
そのまま放置すると筋肉内の血管が圧迫され、最後には死に至ります。
そのため、毎日マッサージや関節を動かすなどして、筋肉の緊張を防ぎ、介護者は患者の生命維持に勤めます。
これは介護で一番大変な作業になります。
このときと同じ筋肉の緊張状態を指します。
この筋肉の状態が見られるのは、ほとんどが腰部です。
※寝たきり患者で無い限り、100%腰部だけにあると言ってもよい
これが、腰の痛みがいつまでも消えない理由です。
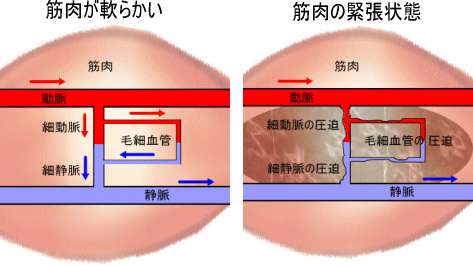
筋肉が軟らかいときは、血流は正常ですが、筋肉が緊張することにより血行不良が起こります。
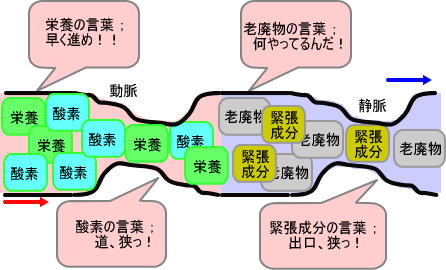
血流が運ばれないと、酸素不足により痛みが発生し、栄養不足からだるさを感じます。
また、静脈が圧迫され場合、老廃物の排出や、筋肉の緊張成分の排出ができないため、いつまでも痛みやだるさが残ります。
※血流が完全に止まった場合、細胞は壊死します。
筋肉が運動している時は、筋肉の収縮運動により静脈のポンプ運動を行っているため、老廃物や緊張させる成分が筋肉から正常に排出されますが、
筋肉が緊張し、運動できない、うまく伸縮できない状態のときは、老廃物や筋肉の緊張成分が筋肉から正常に排出されません。
このため、筋肉はいつまでも緊張状態を維持してしまうのです。
【豆知識】
筋肉を動かしたときの緊張と、動かさない時の緊張の違い
○ 筋肉を動かしたときの緊張
筋肉を筋力以上に動かすと乳酸が大量に発生し、
排出が間に合わなくなり乳酸が滞る。
○ 筋肉を動かさない時の緊張
筋肉の緊張により、筋肉運動の低下から、細静脈、毛細血管の圧迫、
ポンプ機能の低下より緊張成分が滞る。
【ここで一言】
この状態の筋肉になる理由は、人間が2足歩行したためではありません。
ですから犬や猫も当たり前のように慢性腰痛になります。
腰痛になったシマウマは走るのが遅くなりライオンに食べられてしまいます。
この筋肉状態はラット(ねずみ)などの小動物では見られません。
痛みを強く感じるときは緊張した筋肉を伸ばすときです。
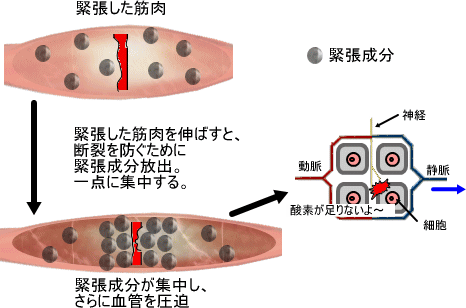
緊張した筋肉を伸ばすとき、筋肉は断裂を防ぐため、緊張成分を大量に放出します。
そのため、筋肉が急激に緊張します。
筋肉が急激に緊張するため、筋線維もしくは筋細繊維間で細動脈や毛細血管で瞬時に過度の血管圧迫が生じます。
そのため、急激に筋細胞に酸素の供給がされないため、激痛と感じます。
この状態が、一般的に言われるぎっくり腰です。
筋肉が断裂したのではなく、緊張している筋肉がさらに緊張した状態です。
ですから、極度に緊張した筋線維の位置を特定し、筋肉を軟らかくできれば5分もしないうちに走ることもできます。
※事故など、筋肉が断裂した場合は、筋肉が修復されるまで痛みが消えません。
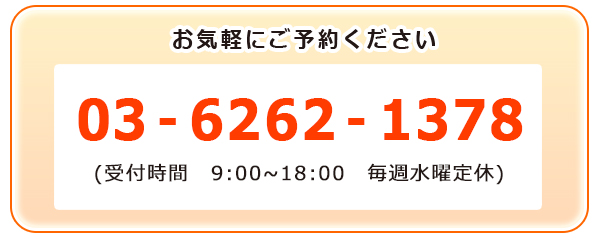 4、筋肉の断裂を繰り返すことによりおこる石灰化・骨化
4、筋肉の断裂を繰り返すことによりおこる石灰化・骨化
※断裂時点での血液検査で、炎症反応が起こるが、凝固・石灰化・骨化後は炎症反応は起こらない。
痛みがあるときは、筋肉の緊張が原因です。
筋肉が緊張するということは、筋肉が硬くなっているということです。
筋肉が硬い = 伸縮がしにくい
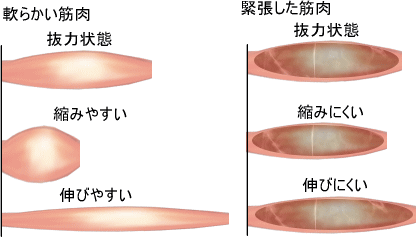
このときに麻酔(痛み止め)を使うと、痛みが無くなりますが、硬くなっている筋肉を無理に伸ばしても痛みが出ませんから、筋肉の線維を断裂させることになります。
※硬くなった輪ゴムがすぐ切れると考えると、わかりやすいです。
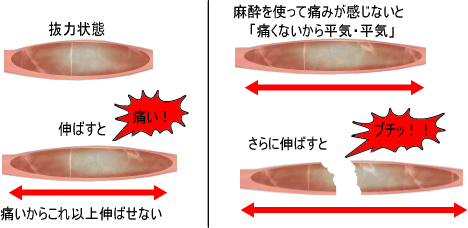
【麻酔の定義】
麻酔とは、痛みがあるときに痛みが無くなる、軽くなる薬全般を指します
痛い場所に直接効かせる麻酔
ブロック注射・局部麻酔(トリガーポイント)・鎮痛剤(飲・座)・湿布(貼・塗)など
脳への麻酔により痛い場所に効かせる麻酔
うつ病の薬・精神安定剤・パーキンソン病の薬など
その他の麻酔
無痛症など、痛みを感じない人も、同じ状態になります。
好きなスポーツで痛みを忘れる程度の場合、痛みの限界を超えて寝たきりになるなどの極度の断裂は通常起こせません。
※薬品の全てを否定しているわけではありません。
薬品の使用は自己責任においてご判断ください。
麻酔が切れると、さらに痛みは強くなったり、体が以前より動きにくくなるのも筋肉の断裂を繰り返したために起こります。
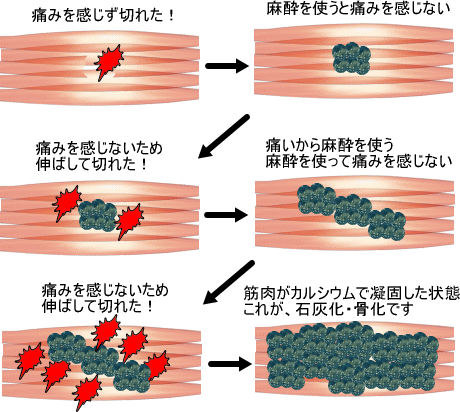
痛みが強くなった場合は、断裂箇所が増えた、断裂周辺の筋肉がさらに緊張した場合です。
体が以前より動かなくなったのも、断裂の箇所が増えたことと、緊張箇所が増えたためです。
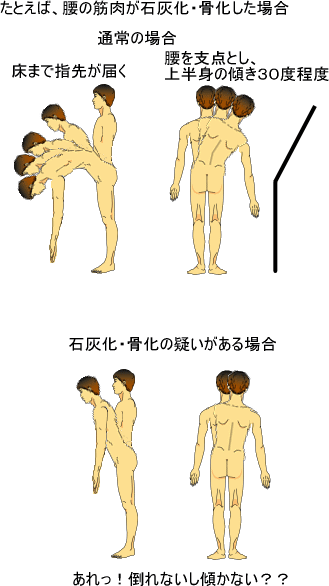
上半身が、左右にも、前後にもまったく動かなくなっている人もいました。
筋肉が凝固した場合は、伸びることができませんから、常に「重い」「だるい」感じを受ける患者がほとんどです。
筋肉が断裂した場所は凝固します。 成分はカルシウムとお話しました。
麻酔を使うなど、痛みを感じないまま筋肉を伸ばし断裂を繰り返すと、カルシウムなどの成分が筋肉の中に常時滞り、範囲も拡大していくために石灰化したり、
さらに断裂を繰り返すことにより、筋肉の骨化につながります。
麻酔を使うと痛みを感じないまま筋肉を伸ばすことができるので、
筋線維が断裂することにより、筋肉の石灰化・骨化につながる。
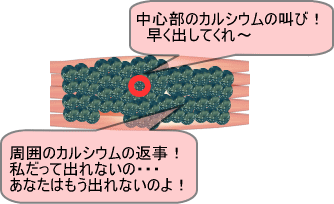
今までも現代医学(臨床現場)で、筋肉の石灰化・骨化は確認されていますが、石灰化・骨化の筋肉を通常の筋肉に再生させる方法はありませんでした。
筋肉の骨化は、特定疾患(難病)にも指定されています。(再生治療方法が無い)
麻酔によって石灰化・骨化した筋肉を抱えた多くの人の協力の下、
2008年5月に再生に成功しています。
通常の筋肉と違い、正常な筋肉に再生するには少し時間がかかります。
立って歩ける状態であれば、2ヶ月以内で再生できています。
麻酔を使い続けた場合でも、ご心配はなさらないでくださいね。
注意!
※ 麻酔の直接影響で筋肉が断裂するわけではありません。
※ そして、必ず断裂し、石灰化・骨化になるわけではありません。
記載のとおり、筋肉の断裂の連鎖は、筋肉を伸ばしたときに起こります。
麻酔を使って安静にしていた場合は起こりません。
激痛に耐え、麻酔を使いながらスポーツを行った場合や、意地になって体を動かしたときに起こります。
今まで調べた中で大量の骨化した筋肉が確認されたのは、
■ 鎮痛剤を1ヶ月使い続け、富士登山マラソンの練習をした。
■ トリガーポイント注射で、柔道の国際大会に出場した。(鎮痛剤常飲)
■ 鎮痛剤を7ヶ月使い続け、力仕事を毎日していた。
■ 結婚間近で車椅子なり、ブロック注射を行い無理に歩いた。(鎮痛剤常飲)
■ 5分立てず、ブロック注射80本、トリガーポイント100本。(鎮痛剤常飲)
いずれにしても、激痛を我慢し麻酔を使い続け、意地になって筋肉を動かし続けた人がほとんどです。
これらの人でも2ヶ月以内には社会復帰ができています。
【豆知識】
凝固させるために必要な大量のカルシウムはどこから来るか??
それは、カルシウムの貯金箱である ”骨” です。
痛みがあるときに、病院で診察を受けると、骨粗鬆症(こつそそうしょう)と診断される場合があります。
これは、骨にカルシウムが少なくなったから痛いのではなく、痛いからカルシウムが筋肉に使われ、骨のカルシウムが減ったと考えるのが自然です。
【補足】
脳の誤作動により、痛みを感じる医学的データ(根拠)はどこにもありません。
麻酔を使い、筋肉の断裂を繰り返すことを知らない医師は、新型腰痛と言っています。
当然、麻酔による筋肉の断裂を知っている医師もいます。
しかし、新型ではありません。 私は薬害と考えています。
※ご理解をお願いします
筋肉を緊張させている全ての成分の公表はいたしません。
医師・製薬会社などの悪用を防ぐため、ご理解をお願いします。
※悪用された場合、筋肉を軟らかくする方法・薬品 筋肉を緊張させる方法・薬品(麻酔)を患者は永遠と受けることになります。
薬品では長い間硬くしたままの筋肉を構造上の問題で軟らかくすることはできませんが、万が一ということもあります。
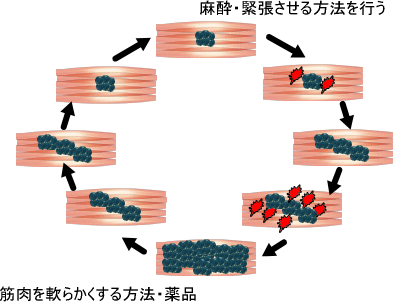
この方法は、痛みに苦しむ患者には直接教えていますのでご安心ください。
大きく分けて4種類の緊張の説明をしましたが、細かく分けると30種類以上の緊張状態が確認されます。
一番早く痛みや痺れを消すためには、この緊張状態を把握し、筋肉を軟らかくしていかなければなりません。
【補足】
現代医学で筋肉を軟らかくできない理由は、筋肉の緊張状態を把握していないことになります。
ラット(ねずみ)などの小動物には、”2、筋肉を動かさないために起こる緊張”の状態にはなりません。
そのため現代医学(臨床現場)では、現在でも筋肉の緊張=痛みについて解明できていないのが現状です。
ある意味、仕方が無いことなのです。
次は、『痛みが消える仕組み』へ
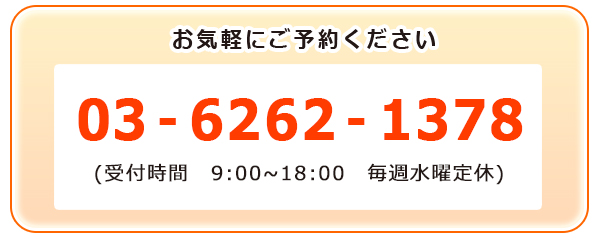




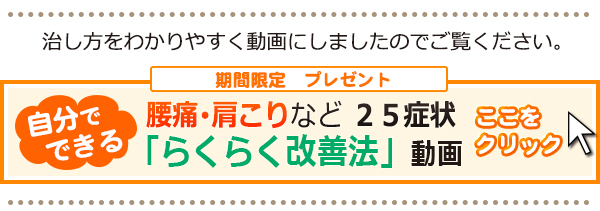
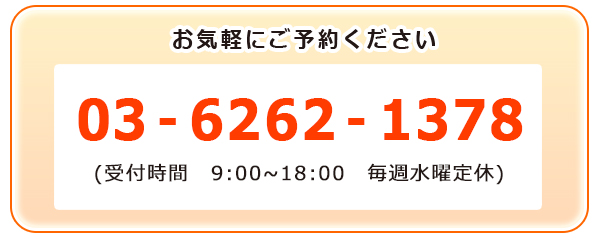 2、筋肉を動かさないために起こる緊張 ※血液検査で、炎症反応が起らない。
2、筋肉を動かさないために起こる緊張 ※血液検査で、炎症反応が起らない。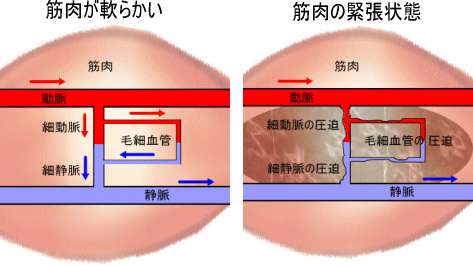
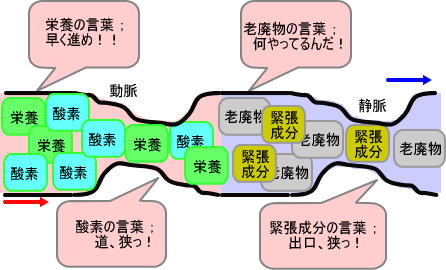
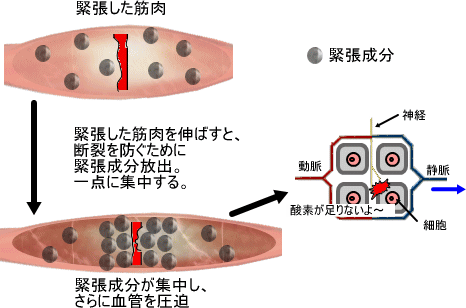
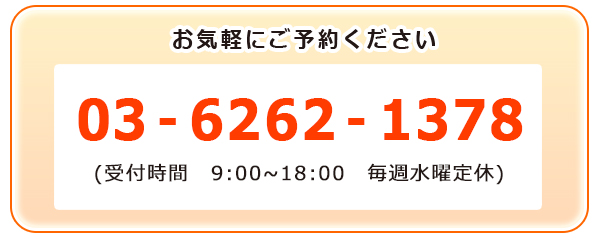 3、筋肉の断裂による凝固から、断裂周囲の緊張
3、筋肉の断裂による凝固から、断裂周囲の緊張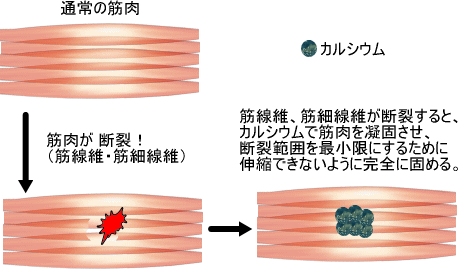
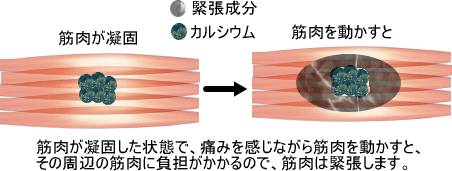
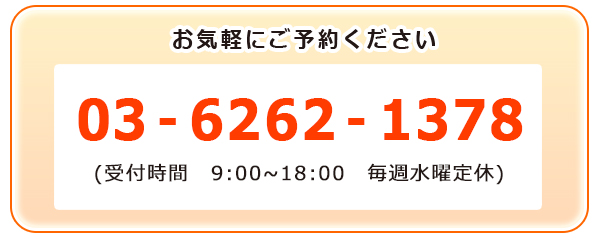 4、筋肉の断裂を繰り返すことによりおこる石灰化・骨化
4、筋肉の断裂を繰り返すことによりおこる石灰化・骨化